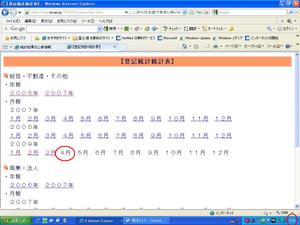「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について
《該当分野一覧》
各見出しに対応するアルファベット(A~K)を「該当分野記号」として記入願います。
A デジタル新時代への戦略(案)全般に係る意見
第1章 総論
B Ⅰ.2015年の我が国とデジタル社会の将来ビジョン
C Ⅱ.我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点
D Ⅲ.本戦略のスコープ
第2章 分野別の戦略
Ⅰ.三大重点分野
E (1)電子政府・電子自治体分野
F (2)医療・健康分野
G (3)教育・人財分野
H Ⅱ.産業・地域の活性化及び新産業の育成
I Ⅲ.デジタル基盤の整備
第3章 戦略的に一層の検討を行うべき事項
J Ⅰ.規制・制度・慣行の「重点点検」
K Ⅱ.「デジタルグローバルビジョン(仮称)」の策定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html
1.. 個人/団体の別
2.. 氏名/団体名
3.. 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
C Ⅱ.我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点
5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
2p
6.. ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
これまでの戦略の経緯と問題点の認識が甘い。「利用者の視点で」と言葉
ではいくらでも言えることで、具体的な方策の工程と責任を決めて評価し、
必ずその責任を果たすべきだ。
7.. ご意見(本文)
なんども同じようなアンケートを繰り返すのではなく、ひとつずつ問題点
を修 正しながら、ひとつずつ解決し、解決したら、またアンケートをと
って、問題点を見つけていくべきだ。
なぜ同じようなアンケートを繰り返すのかというと、認識が甘いと同時に責任
の所在が明確になっておらず、また責任を執ることが一切ないからだ。これで
は、実効ある戦略が果たされるわけがない。
未曾有の電子政府構想なのだから、試行錯誤は仕方のないことで、それでも、
何度も同じことを聞いては同じことを回答していたのでは、国民のやる気はう
せるばかりだ。責任を取らない行政に対して、国民は協力はしない。
費用対効果は当然であるが、効果があがらなかったときの責任の取り方を明確
にして、駄目なら引き返す勇気も必要だ。とにかく、いい加減に進歩の過程を
見せてほしい。
※
4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
E (1)電子政府・電子自治体分野
5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
4p
6.. ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
(将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項を、2009年度末といわず早期に基
本構想とし、必ず工程表にしたがって推進し、目標達成できないときはその責任
を取ること。
7.. ご意見(本文)
(将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項は、今すぐ解決できる喫緊の課題であ
るから、2009年末ではなく、すぐさま取り掛かるべきだ。とくに2(1)に
ある、ペーパーレス化や添付書類の廃止は、すぐにできることから、試行錯誤や
実証実験でよいので、取り組むべきだ。
たとえば、不動産登記の添付書類の省略は、オンライン特有の取り組みができる
わけで、現状のように、逆に登記原因証明情報を必須添付としていたのでは、オ
ンラインの実効性に逆効果となっている。資格者たる司法書士・土地家屋調査士
しか取り組まない不動産登記のオンラインなのに、なぜに資格者を信頼して添付
書類を廃止しないのか、理由が分からない。
すでにe-taxでは、添付書類の廃止によって爆発的に申告数が伸びたことは証明さ
れているのだから、それに習って行うべき価値判断があってよい。
国民のためどれほどの血税を投入した登記オンライン計画なのか明らかにされて
いない(人件費抜きで20年で1兆円といわれるhttp://www.cao.go.jp/bunken- kaikaku/iinkai/kaisai/dai36/36shiryou12.pdf)が、これを必ずや実効あるものにする
ためには、資格者を活用するしかないのであって、そのために必要なことはなに
か?(たとえば、倫理性の高いオンライン専門資格の創設)を考える時期にきて
いると考える。
フランスやドイツを見習って、資格者をうまく活用しないと、オンラインは進ま
ないと断言する。
※
4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
J Ⅰ.規制・制度・慣行の「重点点検」
5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
21p
6.. ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度を見直すといいながら、そ
の最たる例の不動産登記の登記識別情報制度を、一向に解決しないのは、行政の
不作為・怠慢だ。
7.. ご意見(本文)
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組
みそのものの在り方や運用などを国民にとって利益となる形で抜本的に見直すこ
とが必要である。」この点については、全面的に賛成である。
しかし、「このため2009年中を目途に、第一次の「重点点検」を行い、その結果
を踏まえ、政府として所要の措置を講ずる。」というのは、遅きにすぎる。すで
に、表記の不動産登記の「登記識別情報制度」についての問題性は経済性、安全
性、対オンライン性の観点から、明らかになっている。形ばかりの「偽装オンラ
イン」を続けて数あわせをしても、所詮、オンライン化のひとつの目的である事
務効率化は図れていない。
また、国民負担はこの登記識別情報制度のおかげで、管理や紛失の危険にまつわ
るさまざまなトラブルが懸念されている。したがって、直ちにこの制度は廃止し
て、新しい仕組みを、登記オンラインの現場で関わる司法書士や土地家屋調査士
とともに、一から、しかも早急に、構築する必要がある。
その際は、法務省も認識しているとおり、「オンライン申請の利用者満足度に関
するアンケート調査 (平成21年6月7日新設)」 http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.htmlの結果を踏まえて、ひとつずつ問
題を解決すべきである。解決してはじめて次のアンケートなりパブコメをすべき
だ。
また、「IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会(第3回)」資料http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai3/3gijisidai.html(「デジタルジ
ャパン」の原案等の策定に関するパブリックコメント)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/pubcom/05.pdfにも申し上げたけれ
ども、この調査会をはじめとして、まったく議事にもなっていないのはなぜか?
パブコメをして集めてHPに掲載して、それでおわりにするのか?その点を明ら
かにする必要がある。
きしくも、同じことが、法務省民事局の「新オンライン登記申請システム骨子案
に対する意見募集について」のパブリックコメントhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.htmlにおいても、なされようとしておる。問題
のある登記識別情報制度を残したまま、新オンラインシステムを構築することが
どれほど無駄なことか、分かっているのにも関わらず、だれも改革も責任もとれ
ないままだ。いい加減にしてほしい。
こんなことをいつまでも同じことを繰り返すのであれば、オンライン政策そのも
のを頭から否定することにもなりかねない。このままでは、進歩のない議論を繰
り返すIT戦略本部というレッテルを貼らざるを得ず、IT戦略本部そのものに
かかっている経費を見直す必要があると考える。