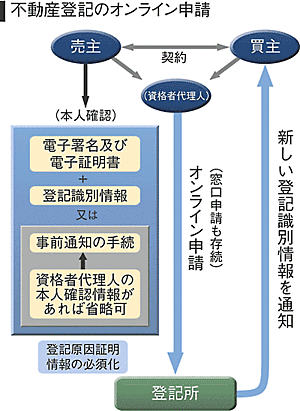ジャーナリスト 千葉利宏さん、検証してますか?
<テイクオフe-Japan戦略II>11.不動産のオンライン登記
電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。(ジャーナリスト 千葉利宏)
利活用の環境づくりを
電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。「不動産登記法は、基本的な枠組みが明治時代以来100年間ほとんど変わっていなかったが、オンライン化によって全てを見直す必要が出てきており、現代語化を含めた法改正を準備している」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。法務省では、2年以上前から不動産のオンライン登記に向けた調査研究を開始。今年3月にまとまった報告書を受けて、7月に法改正の担当者骨子案を公表しパブリックコメントを募集。先月、法制審議会に諮問して、改正法案を来春の通常国会には提出したい考えだ。
現行の不動産登記制度は、登記の申請は本人確認のために登記所への「出頭主義」が明記されており、全ての申請情報は「書面」で提出し、登記の完了時には紙の「登記済証」が交付される“紙”を前提とした仕組みとなっている。オンライン化を実現するためには、これら出頭主義、書面、登記済証を全て廃止して、制度全体を再構築する必要があるわけだ。
現在審議中の新制度では、これまで本人確認手段として利用されてきた登記済証を廃止する代わりに、登記名義人を識別するための「登記識別情報」を通知する方法を導入する。しかし、ID番号のような登記識別情報では取引相手などの他人に見せると、登記済証を盗まれたと同じ状態になってしまうため、登記識別情報を保有していることを証明する制度を新たに導入。また、登記名義人が登記識別情報の管理が大変で、盗まれたり、忘れたりする危険があると判断した場合は、申出により識別情報を「失効」する手続きを取り、登記申請のときに別な方法で本人確認する制度も新設するとしている。
不動産のオンライン登記に関する新制度の枠組みはほぼ固まってきたが、利活用に向けた議論はまだあまり盛り上がっていないのが実情だ。不動産登記の手続きの約95%は、司法書士が代理申請しているが、先月初めに東京司法書士会が主催した市民公開シンポジウム「権利証がなくなる日」では、司法書士関係者から紙の「登記済証」の大切さを強調する発言が相次いだ。以前から、オンライン登記によって司法書士の代理申請需要が減少するとの指摘もあったが、シンポの内容はオンライン登記に対する司法書士の危機感が強く表れた格好と言える。
不動産業界も、現時点ではオンライン登記に対する関心はまだ薄いという印象だ。不動産会社でも不動産登記手続きは司法書士に依頼しているケースがほとんどで、「オンライン登記が導入されても従来どおり司法書士に依頼するのではないか」(大手不動産担当者)との声も聞かれる。ただ、こうした状況もオンライン登記に関する情報不足が原因と考えられ、実際にオンライン登記が動き出し、利活用に向けた環境が整備されれば関心が一気に高まることになるだろう。
一方、個人の利用はどうだろうか。「最近では、名義人本人の申請も非常に増えてきている。住宅ローンが払い終わったあとの抵当権の抹消手続きや、親族間での登記といったケースが多い」(小宮山補佐官)。法務省では、オンライン登記用の申請書作成ソフトを無償で配布(ダウンロード)することにしており、手続きが比較的に簡単なものから、個人でもオンライン登記の利用が広がっていきそうだ。
100年ぶりに大きく生まれ変わる不動産登記制度――。紙から電子へと移行する衝撃が大きすぎるためか、前向きに取り組む動きがまだ芽生えていないという印象もある。しかし、司法書士にとっても、不動産会社や金融機関などのユーザー企業にとっても不動産登記業務を効率化しようという潜在需要はあるはず。これらを顕在化させ、オンライン登記の利活用を進めていくことが、ITベンダーにとっても新たなビジネスチャンスを生むことにつながるのではないだろうか。